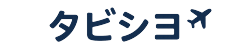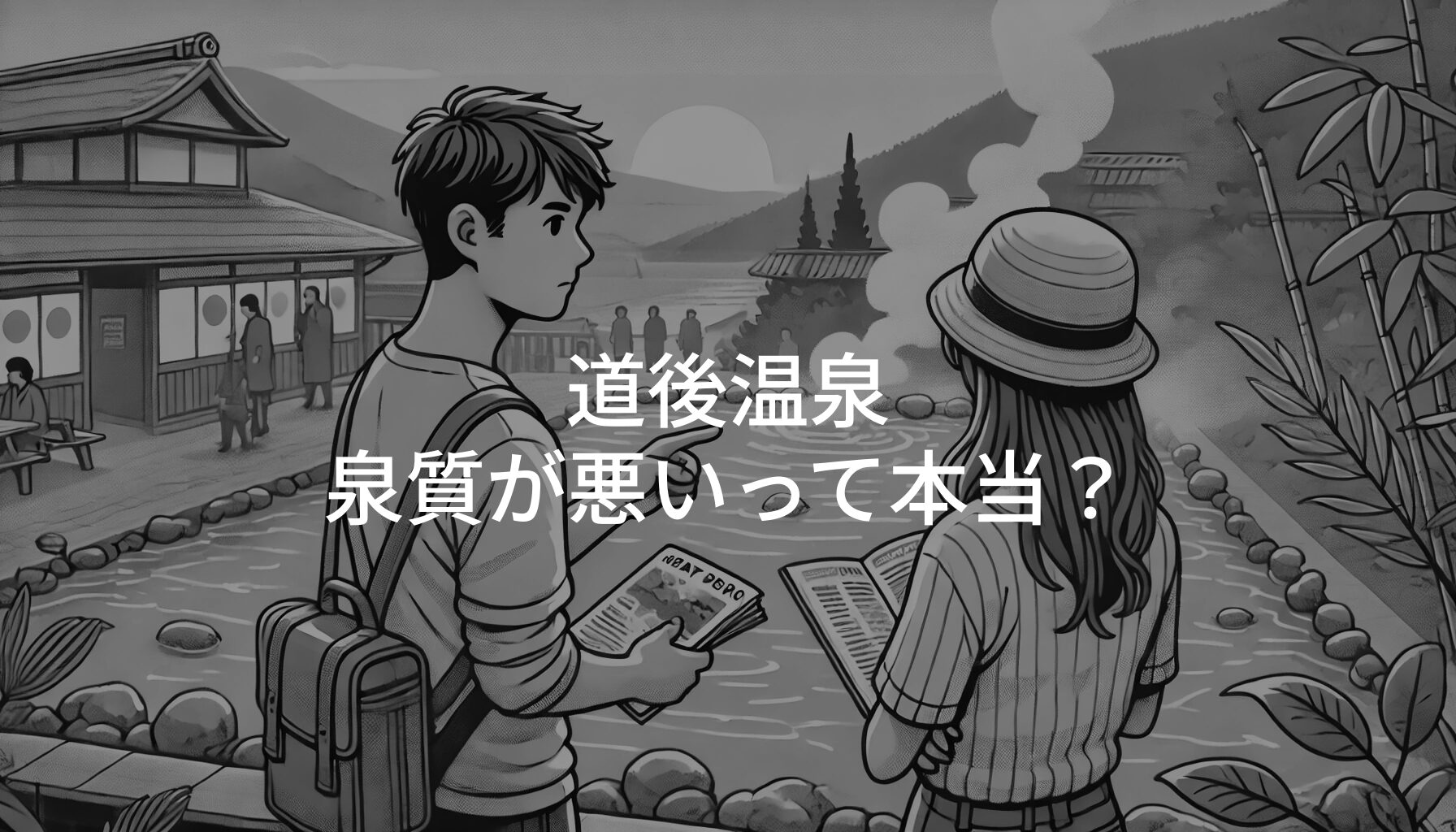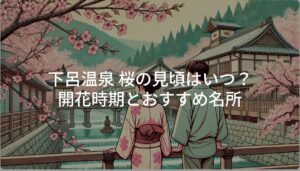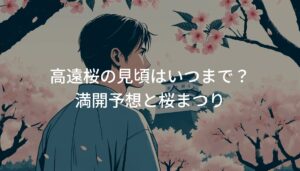道後温泉は、泉質の特徴から「泉質が悪い」と感じる方もいて、中には「温泉じゃない」「やばい」といった否定的な意見を持つ人もいます。
道後温泉の泉質は何性なのか、本当に泉質が悪いと言えるのでしょうか。
この記事では、道後温泉の泉質の特徴や評価が分かれる理由を詳しく解説し、温泉としての魅力や楽しみ方も紹介します。
道後温泉に行くべきか迷っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
- 道後温泉の泉質の特徴や泉質は何性なのかについて
- 温泉じゃないと言われる理由やその誤解について
- やばい・最悪といわれる口コミの背景や実際の評価
- 道後温泉の歴史的価値や観光地としての魅力
道後温泉の泉質が悪い?と感じる理由

- 道後温泉の泉質は何性ですか?
- 温泉じゃないと言われる背景
- 熱いと感じる人への対策
- 源泉は枯渇しているのか
道後温泉の泉質は何性ですか?
道後温泉の泉質は「アルカリ性単純温泉」に分類されます。
単純温泉とは、温泉水中の溶存物質が1000mg未満で、源泉の温度が25℃以上のものを指します。
道後温泉のpH値は9.1と高めで、アルカリ性の温泉です。
アルカリ性温泉の特徴として、肌の角質を落としやすくする効果があり、入浴後に肌がすべすべする感覚を得られることが挙げられます。
こうした効果から、「美人の湯」とも呼ばれ、特に女性に人気があります。また、刺激が少ないため、幅広い年代の方に適した泉質です。
一方で、硫黄泉や炭酸泉のような特徴的な香りや色、泡立ちがないため、「温泉らしさ」を期待して訪れた方には物足りなく感じることがあるかもしれません。
無色透明でクセが少ないことが、良くも悪くも評価が分かれるポイントです。
温泉じゃないと言われる背景
道後温泉が「温泉じゃない」と言われる背景には、泉質や管理方法に関する誤解があります。
道後温泉は源泉かけ流しの温泉ですが、殺菌のための塩素消毒が行われており、その影響で「塩素臭がする」と感じる人がいるため、温泉特有の風情を求める方には違和感があるようです。
また、道後温泉の泉質が単純泉であることも、温泉らしくないと感じられる要因の一つです。
有馬温泉の金泉のような濃厚な成分や、草津温泉の強い酸性泉とは異なり、見た目や香りに特徴が少ないため、「普通のお湯と変わらない」と思われがちです。
さらに、道後温泉本館は日本最古の温泉とされる一方で、温泉の利用方法が公衆浴場に近いため、温泉地の雰囲気を重視する人には「大衆浴場の延長のように感じる」との声もあります。
しかし、源泉かけ流しであることや、歴史的価値を持つ温泉である点を考えると、れっきとした温泉であることは間違いありません。
熱いと感じる人への対策
道後温泉は、源泉の温度が42℃~51℃と比較的高温であるため、「お湯が熱い」と感じる人も少なくありません。
特に、普段からぬるめのお湯に慣れている方や長湯を楽しみたい方にとっては、熱すぎると感じることがあるでしょう。
対策として、まずおすすめなのが「かけ湯」をして体を慣らすことです。
急に熱いお湯に入ると、体がびっくりしてしまうため、少しずつ温度に慣らしてから入浴すると快適に楽しめます。
また、長時間の入浴を避け、こまめに浴槽から出ることで、のぼせるのを防ぐことができます。
道後温泉の本館では、浴槽の端に座って半身浴をすることで、熱さを軽減することも可能です。
ただし、マナーとして他の利用者の迷惑にならないよう注意が必要です。
ホテルや旅館の道後温泉のお風呂を利用する場合は、水を足して温度調整ができる施設もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、道後温泉には別館の「飛鳥乃湯泉」や宿泊施設の温泉もあり、比較的入りやすい温度に調整されていることが多いです。
熱すぎると感じる場合は、異なる施設を選択するのも一つの方法です。
源泉は枯渇しているのか
道後温泉の源泉が「枯渇しているのではないか?」という疑問を持つ人がいますが、現在のところ枯渇の心配はありません。
道後温泉では、18本の源泉から温泉を汲み上げており、それらをブレンドすることで適温を保つ仕組みになっています。
しかし、温泉資源の保護と持続可能な利用を考慮し、一部の源泉を間引いて利用するなど、管理が行われています。
また、観光客の増加に伴い、一時的に湯量の調整が行われることがありますが、これは枯渇ではなく、温泉の適切な運用のための措置です。
温泉の湧出量が減少することを防ぐため、道後温泉では持続可能な温泉管理が実施されています。そのため、今後も適切な調整のもとで温泉が利用され続けるでしょう。
枯渇を心配する必要はなく、訪れる際は歴史ある温泉を安心して楽しむことができます。
道後温泉の泉質が悪い?本当の魅力

- 最悪・やばいと言われる理由
- つまらない?観光の楽しみ方
- 歴史的価値とは?文化財としての魅力
- 他の名湯と比較!違いを徹底解説
最悪・やばいと言われる理由
道後温泉は、日本三古湯のひとつとして長い歴史を持ち、多くの観光客が訪れる人気の温泉地です。しかし、一部の訪問者から「最悪」「やばい」といった否定的な意見が見られることもあります。
その理由として、大きく以下の点が挙げられます。
まず、泉質に対する期待とのギャップです。
道後温泉の泉質は「アルカリ性単純温泉」で、無色透明・無臭のため、硫黄泉や炭酸泉のような特徴的な泉質を求める人には物足りなく感じられることがあります。
「温泉らしさを感じなかった」という意見も、この点に由来していると考えられます。
次に、塩素臭が気になるという声です。
道後温泉では衛生管理のため塩素消毒が行われていますが、その匂いが気になる人もいます。
特に、「温泉ならではの自然な湯の香りを楽しみたかった」という方にとっては、違和感を覚える要因になっています。
また、混雑の問題もあります。
道後温泉本館は観光名所としても有名なため、特に観光シーズンや週末には多くの人が訪れます。
そのため、「人が多すぎて落ち着けなかった」「ゆっくり浸かれなかった」といった口コミも少なくありません。
とはいえ、道後温泉は歴史的建造物としての価値があり、文化財に指定されている本館の雰囲気を楽しむことができます。
訪れる時間帯を工夫することで、混雑を避けながら温泉を満喫できるでしょう。
つまらない?観光の楽しみ方
「道後温泉はつまらない」という声があるのは、温泉だけを目的に訪れた人が期待外れと感じることがあるためです。
しかし、道後温泉は温泉以外にも多くの観光スポットや楽しみ方があり、工夫次第で充実した旅行を楽しむことができます。
まず、道後温泉本館だけでなく「飛鳥乃湯泉」などの別館もあるため、異なる雰囲気の温泉を体験することができます。
本館は歴史的な趣を感じる建物であり、飛鳥乃湯泉は比較的新しく、より落ち着いた環境で入浴を楽しめるのが特徴です。
また、道後温泉周辺には「道後ハイカラ通り」と呼ばれる商店街があり、地元のグルメやお土産を楽しむことができます。
名物の「じゃこカツ」や「坊っちゃん団子」、地ビールなどを味わいながら散策するのもおすすめです。
さらに、道後温泉は「千と千尋の神隠し」のモデルの一つとも言われており、夜にはライトアップされた道後温泉本館が幻想的な雰囲気を醸し出します。
映画の世界観を感じながら写真を撮るのも楽しみ方の一つです。
温泉以外にも松山城や坂の上の雲ミュージアムなど、歴史や文化を楽しめるスポットが近隣に点在しているため、道後温泉を拠点に観光を広げることもできます。
温泉だけでなく、周辺の魅力も組み合わせることで、より充実した旅になるでしょう。
歴史的価値とは?文化財としての魅力
道後温泉は、日本最古の温泉の一つとして知られ、その歴史は3000年以上に及びます。
この長い歴史の中で、多くの偉人や文化人に愛されてきたことが大きな魅力です。
特に、道後温泉本館は明治時代に建てられ、現存する公衆浴場としては珍しい「国の重要文化財」に指定されています。
この本館の建築は、伝統的な和風建築と西洋建築の要素が融合した独特なデザインが特徴で、屋上には「振鷺閣(しんろかく)」と呼ばれる塔屋があり、ここから時を告げる太鼓の音が響き渡ります。
この「刻太鼓」は「残したい日本の音風景100選」にも選ばれており、温泉街の情緒を一層引き立てています。
また、道後温泉の歴史には伝説も多く残されています。
古代には、足に傷を負った白鷺が温泉に浸かり傷を癒したという「白鷺伝説」や、神話の時代に少彦名命(すくなびこなのみこと)がこの温泉に浸かって病を癒したという話が伝わっています。
これらの伝説が、道後温泉の神秘性を高める要素となっています。
さらに、明治時代の改築を主導した初代道後湯之町町長・伊佐庭如矢(いさにわゆきや)は、「100年後にも価値がある温泉施設を作る」という信念のもと、大規模な改築を行いました。
この結果、道後温泉本館は今なお多くの観光客を魅了し続ける文化財となっています。
ただし、歴史的価値がある反面、現在は老朽化が進んでおり、修復工事が行われています。
そのため、一部の施設が利用できない期間があることには注意が必要です。それでも、歴史を感じながら温泉に浸かる体験は他の温泉地では味わえない特別なものです。
道後温泉と他の名湯を比較!違いを徹底解説
日本には数多くの名湯がありますが、道後温泉はその中でも独自の特徴を持っています。
ここでは、有馬温泉(兵庫)、草津温泉(群馬)と比較しながら、道後温泉の違いを解説します。
泉質の違い
道後温泉の泉質は「アルカリ性単純温泉」で、pH9.1と高めです。
刺激が少なく、肌を滑らかにする効果があるため「美人の湯」として知られています。
一方で、硫黄泉や炭酸泉のような特徴的な匂いや色はなく、温泉に「特別な効能」を求める人には物足りなく感じられることもあります。
・有馬温泉(兵庫):金泉(含鉄強塩泉)と銀泉(炭酸泉)があり、特に金泉は赤褐色で塩分や鉄分を豊富に含むため、保温・保湿効果が高い。
・草津温泉(群馬):強酸性の硫黄泉で、殺菌力が強く皮膚病や慢性疾患に効果があるとされる。独特の硫黄臭が特徴。
温泉の雰囲気
道後温泉は、歴史ある温泉地でありながら、都市部の松山に近くアクセスが良いのが特徴です。
周囲にはホテルや商店街があり、観光客にとって便利な環境が整っています。
・有馬温泉:山間部に位置し、古くから湯治場として栄えた。高級旅館が多く、大人向けの落ち着いた雰囲気。
・草津温泉:温泉街の中心に「湯畑」があり、常に温泉が湧き出している景観が楽しめる。大衆浴場も多く、リーズナブルに温泉を楽しめる。
観光・アクティビティ
道後温泉の魅力は、温泉だけでなく観光やグルメも充実している点にあります。
「道後ハイカラ通り」では坊っちゃん団子やじゃこカツなどの地元グルメを楽しめるほか、周辺には松山城や坂の上の雲ミュージアムなど歴史的スポットも豊富です。
・有馬温泉:温泉街自体はコンパクトだが、神戸の観光地(三宮、六甲山など)へのアクセスが良い。
・草津温泉:温泉の湯もみ体験ができるほか、近隣にはスキー場やハイキングスポットがある。
総じて、道後温泉は「歴史と文化を感じられる温泉地」としての魅力が強く、温泉そのものの効能よりも、街歩きや観光を重視したい人に向いている温泉地と言えます。
まとめ:道後温泉の泉質が悪いと言われるポイント
- 道後温泉の泉質はアルカリ性単純温泉でpH9.1の高めの値を持つ
- 肌の角質を落としやすく、美肌効果が期待される
- 硫黄泉や炭酸泉のような特徴的な匂いや色がないため物足りなく感じる人もいる
- 無色透明で刺激が少なく、万人向けの温泉として評価される
- 殺菌のため塩素消毒が施されており、塩素臭を気にする声がある
- 観光客が多く、混雑しやすいため落ち着けないと感じることもある
- 道後温泉本館は公衆浴場のようなシステムで温泉地らしさを求める人には不満が残る
- 源泉の温度が42℃~51℃と高く、熱すぎると感じる人もいる
- 「かけ湯」や半身浴などで熱さに慣れる工夫が必要
- 道後温泉の源泉は枯渇しておらず、適切に管理され持続的に利用されている
- 「最悪・やばい」と言われることもあるが、歴史的な価値の高さが魅力の一つ
- 温泉そのものを楽しむよりも観光や文化を楽しむ温泉地として人気がある
- 「道後ハイカラ通り」では地元グルメやお土産を楽しめる
- 「千と千尋の神隠し」のモデルとされる建物の雰囲気を味わえる
- 有馬温泉や草津温泉とは泉質や雰囲気が異なり、歴史と文化を重視する人に向いている